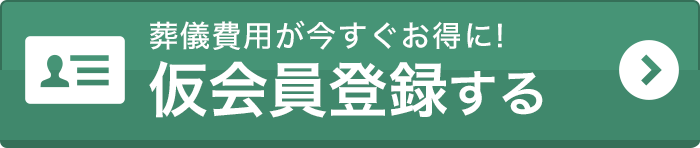お葬式がはじめての⽅ | 盛岡市の葬儀・家族葬なら駒木葬祭
お葬式がはじめての⽅ BEGINNER
⼤切なご家族の⽅が亡くなり精神的にも⾁体的にも計り知れない深い悲しみの中、
故⼈の葬儀を執り⾏われなければなりません。
⼼を込めて故⼈の旅⽴ちを⾒送る事は
残された家族の努めでもあり最後のお別れをする⼤切な時間でもあります。
しかし、いざ⾃分が喪主となった時、どうすればいいのか、何をしたらいいのか分からない場合、
慌てずに故⼈のお⾒送りができるように知っておきたい事をご紹介いたします。
葬儀の費⽤は
どのくらいかかるの?
葬儀にかかる費⽤は3つの費⽤から成り⽴ちます。

基本費⽤
基本項⽬祭壇⼀式、お⾻箱・
位牌など

飲⾷接待費⽤会葬品・通夜ぶるまい・
法事料理など

お納めするお布施
お布施、お⾞代等
知っておきたいこと
葬儀社によっては、基本費⽤の中に会館の使⽤料が含まれず、別途費⽤が発⽣する場合がございます。
また、ご遺体の痛み進⾏を遅らせるためのドライアイスや遺影写真の引き伸ばし加⼯などもオプションとされるところがございます
駒⽊葬祭なら
葬儀に必要な項⽬
(ドライアイス含む)
会館使⽤料
遺影写真の引き伸ばしなど
含んで
家族葬が 48 万円〜(税抜)
駒⽊葬祭が
お⼿伝いできること
- 寺院や教会などへのご挨拶
- お布施に関するサポート(タイミングや作法等)
- スケジュールや作法の確認
- 通夜ぶるまいや法事料理・⼿配
- 喪主の挨拶(例⽂)等
- 弔電や⽣花の順番や、会⾷の時の席順などのご案内
- ⽕葬場のサポート
- 弔意の受け⽅
- お⼿伝いをしてくださる⽅々のサポート
- 喪服のレンタルと着付の⼿配(※ご希望の場合)
- 遠⽅から来られる⽅々の宿泊の⼿配(※ご希望の場合)
- 後飾り祭壇の設置
- 四⼗九⽇や百か⽇などの年忌法要のお⼿伝い
無料事前相談
葬儀のことなら何でもご相談ください
- 葬儀にかかる費⽤について知りたい
- 葬儀の流れなど説明を聞きたい
- 会館の雰囲気や設備を確認したい
まず 何から準備
したらいいですか?
⼤切な⽅との別れが突然訪れた場合、事前に準備しているかどうかで、⼼労や費⽤が⼤きく異なります。
故⼈が望んでいた葬儀の形式や、⾃分たちに合った葬儀の形を考え、前もって決めておくことをお勧めします。万が⼀の際に備え、今から準備を整えておきましょう。
どのように進めたらいいか分からないかや、⼀般的な内容も確認しながら決めていきたいなど、葬儀のことでお困りでしたら駒⽊葬祭にお電話ください。
専⾨のスタッフが対応いたします。次に近親者の⽅や親しい⽅へ訃報の連絡をしてください。
ご葬儀までに決めること
-

安置する場所
-

参列者
-

⽇程
-

遺影写真
-

葬儀の内容
-

返礼品や
通夜ぶるまい
法事の料理 -

通夜・⽕葬場・
葬儀の時の挨拶
やお⾒送り
喪主について
ご家族の誰かが亡くなってしまった時、最初に決めなければならないのが喪主です。
喪主は遺族の代表です。葬儀に関する様々な事を決めていくことになります。
故⼈に⼀番近い⽅が務めるのが望ましいです。配偶者の⽅、⼜はご⻑男、姉弟の⽅が務めるのが⼀般的です。(配偶者も⾎縁者もいらっしゃらない場合は友⼈、知⼈の⽅などが務める場合もあります)また、喪主は故⼈の代わりに⽣前お世話になった皆様に最後のご挨拶を伝える事も⼤切な役⽬です。
何からやればいいのかわからない。と、とても不安になってしまうものだと思います。駒⽊葬祭でしっかりとサポートいたしますのでご安⼼ください。
葬儀の流れ
葬儀を執り⾏う際には、多くの準備が必要で、次から次へとやるべきことが押し寄せます。
ここでは、葬儀前の準備から式の終了までの⼀連の流れと、葬儀プランを事前に検討したい⽅のために、役⽴つ情報をご紹介いたします。
※宗派によって異なる場合があります。
-

- 1. 危篤・臨終・ご逝去
- 危篤の連絡を受けたら、近親者や最後に会ってもらいたい⽅々に連絡をします。
(事前に連絡する⽅を決めてリスト等にしておくと安⼼です)
ご逝去後は死亡診断書の受け取りや死亡届の提出などの役所⼿続きを順次進めていきます。
-

- 2. 搬送葬儀社の⼿配・搬送
- 故⼈のご臨終後、葬儀社の⼿配が必要になるので、まずは駒⽊葬祭にご連絡ください。(0120-09-2343)
24時間365⽇対応しております。
安置場所をご⾃宅にされるか通夜会場にされるか決めておくとスムーズです。※ご⾃宅前経由での搬送も可能です。
-

- 3. 葬儀社との打ち合わせ
- 葬儀社との打ち合わせでは、限られた時間内に多くのことを決定しなければなりません。
最初に葬儀の⽇取り、場所、規模を設定し、その後、祭壇の種類や棺、⾻壺、戒名、遺影など詳細を順に決めていきます。
-

- 4. 納棺
- 納棺は、故⼈の⾝体を清めて副葬品と共に棺に収める儀式を指します。仏⾐をお着せして、棺に納めます。
-

- 5. 通夜
- 通夜は多くの⼈が集まり、故⼈を弔う重要な儀式です。
遺族は会葬者に挨拶をしたり、通夜のあとに故⼈と最後の⾷事(通夜ぶるまい)をともにするもてなしをします。
-

- 6. ⽕葬
- ⽕葬場に向かい、⽕葬後は収⾻をおこないます。
最後に会葬者に挨拶をし、お寺もしくは会館に移動します。
-

- 7. 葬儀
- 火葬後にお寺または会館で葬儀(告別式)が執り⾏われます。
葬儀が終わると、喪主や親族代表が参列者に向けて挨拶をします。
-

- 8. 初願忌法要
- 初願忌法要とは葬儀後に三十五日法要などの複数の法要を⼀度にまとめて⾏うことを指します。
何度も法要を⾏う代わりに⼀度にまとめることで、遺族の精神的な負担を軽減し、落ち着いて故⼈を偲ぶ時間を持てるようになります。喪主は導師や出席された⽅にご挨拶します。終了後、親族を中心に会食します。
無料事前相談
葬儀のことなら何でもご相談ください
- 葬儀にかかる費⽤について知りたい
- 葬儀の流れなど説明を聞きたい
- 会館の雰囲気や設備を確認したい
葬儀後にしないと
いけないことは?
⾝内の⽅が亡くなられると、まず通夜や葬儀の準備に追われますが、その後も多くの⼿続きを⾏う必要があります。葬儀が終わるとすぐに、故⼈の年⾦、保険、銀⾏などの諸⼿続きを進めなければなりません。
ご遺族の⽅は、⼼⾝共に疲れている中で⼿続きを進めるのは⼤変ですが、これらの⼿続きには期限が設けられているものが多いため、なるべく早く着⼿することをお勧めします。事前に必要な⼿続きを把握しておくと、スムーズに対応できるでしょう。
休⽌
資格喪失
保険脱退
故⼈が亡くなられてから2週間以内に⾏わなければならないため、葬儀が終わったら、直ちに⼿続きを開始しましょう。
駒⽊葬祭では、
アフターサポートも
充実しています
葬儀が終わったらお付き合いが終わるわけではなく、四⼗九⽇、仏壇、墓⽯、お⾹典返し等のお⼿伝いもさせていただきます。
駒⽊葬祭のやすらぎの会にご⼊会いただきますと、⼀周忌や三回忌の年忌法要にて、供物とお花を無料でサービスいたします。
無料事前相談
葬儀のことなら何でもご相談ください
- 葬儀にかかる費⽤について知りたい
- 葬儀の流れなど説明を聞きたい
- 会館の雰囲気や設備を確認したい





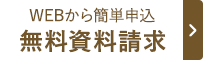
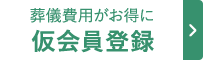
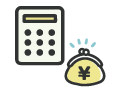 葬儀の費⽤は
葬儀の費⽤は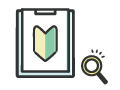 まず何から
まず何から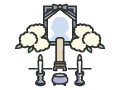 葬儀の流れ
葬儀の流れ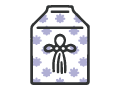 葬儀後に
葬儀後に






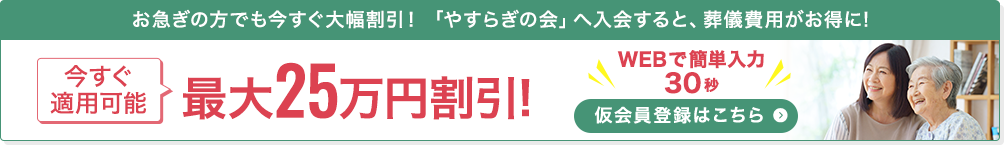
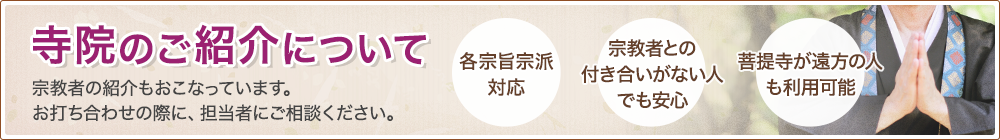
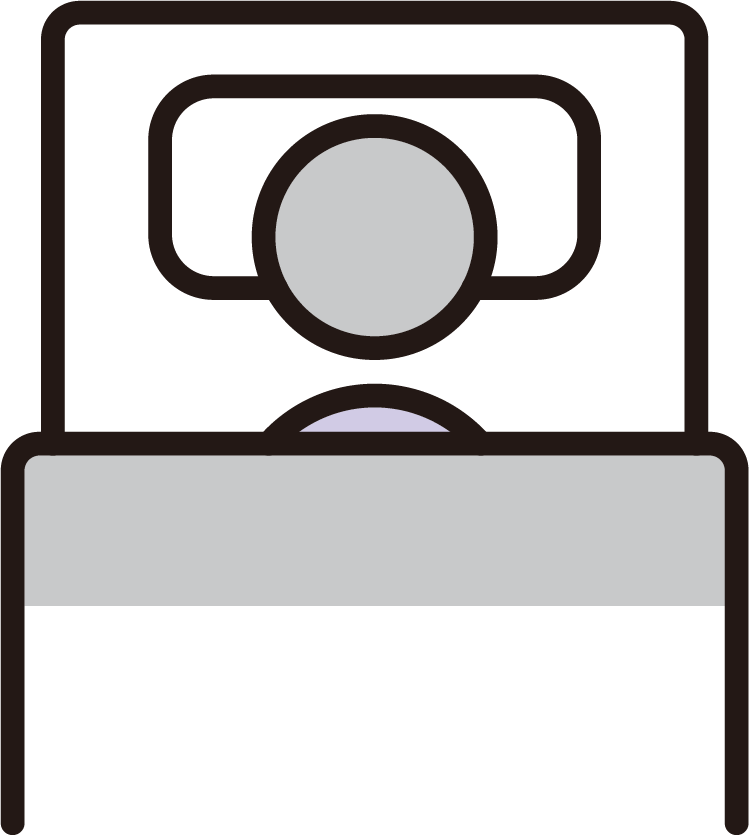
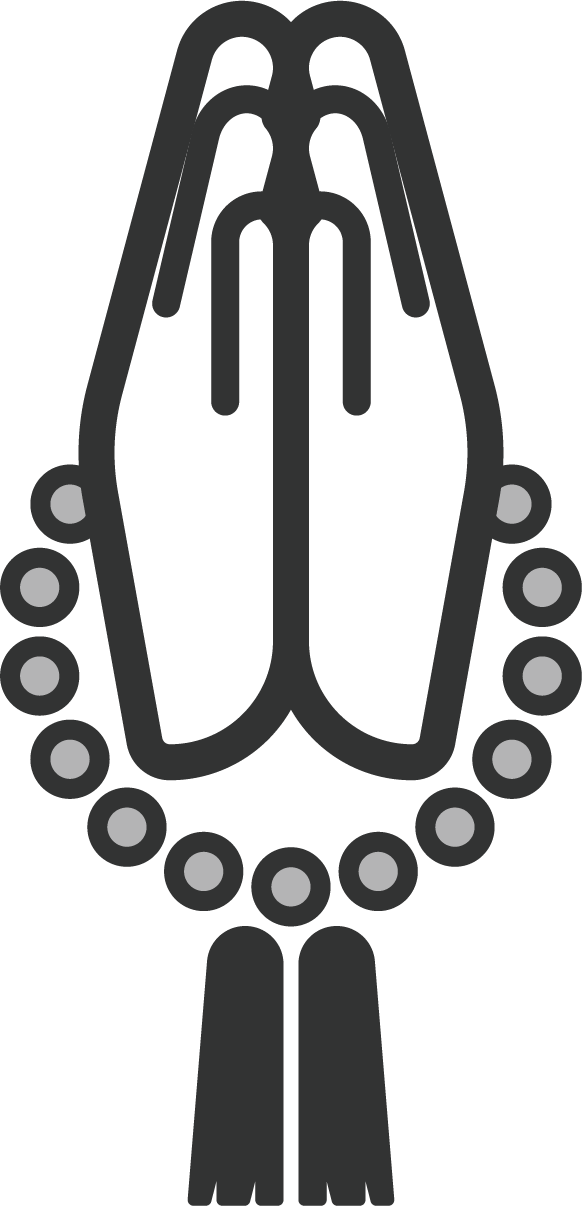
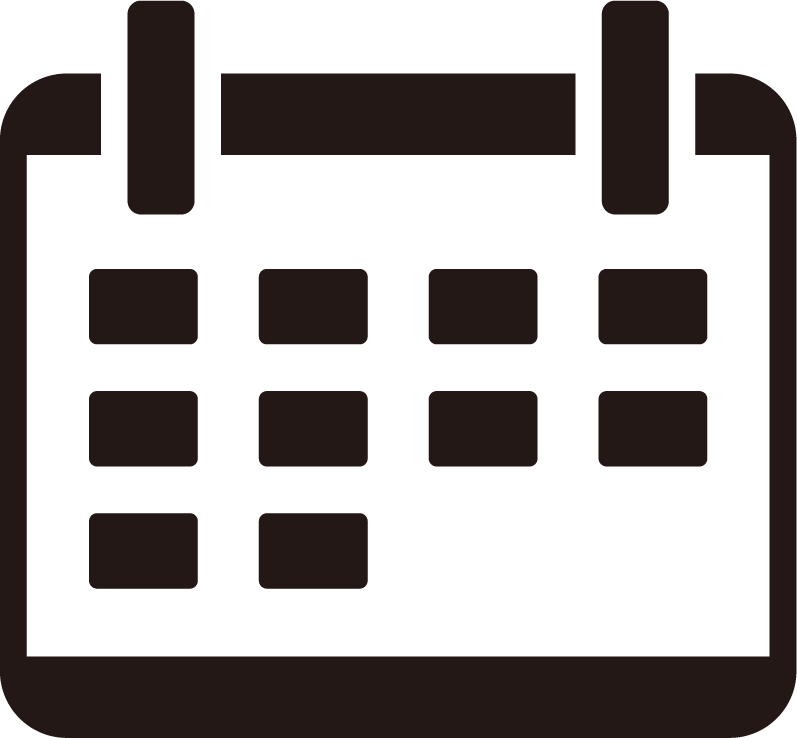
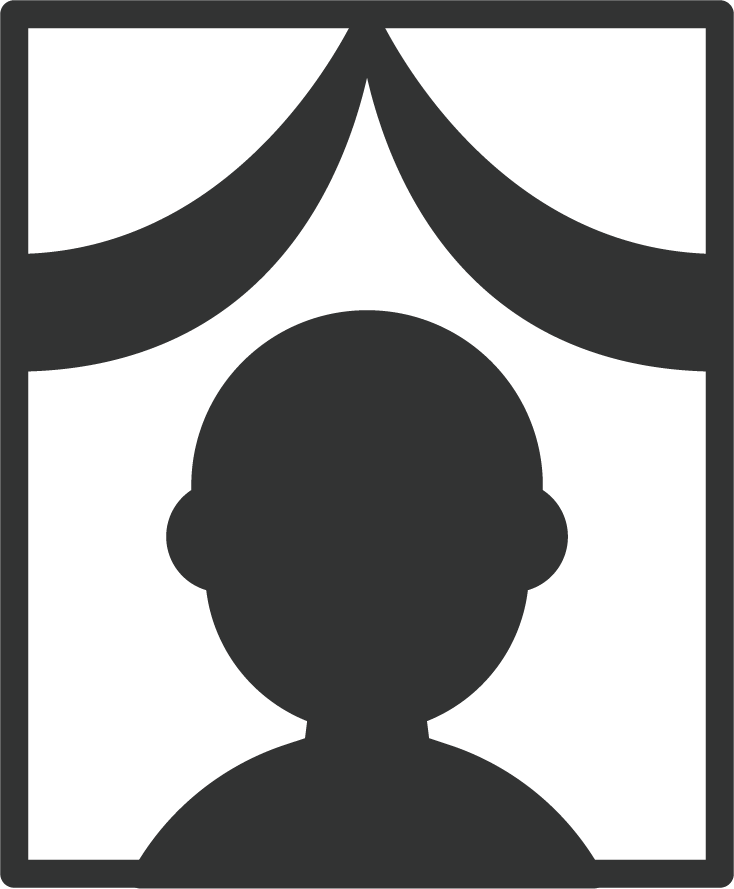
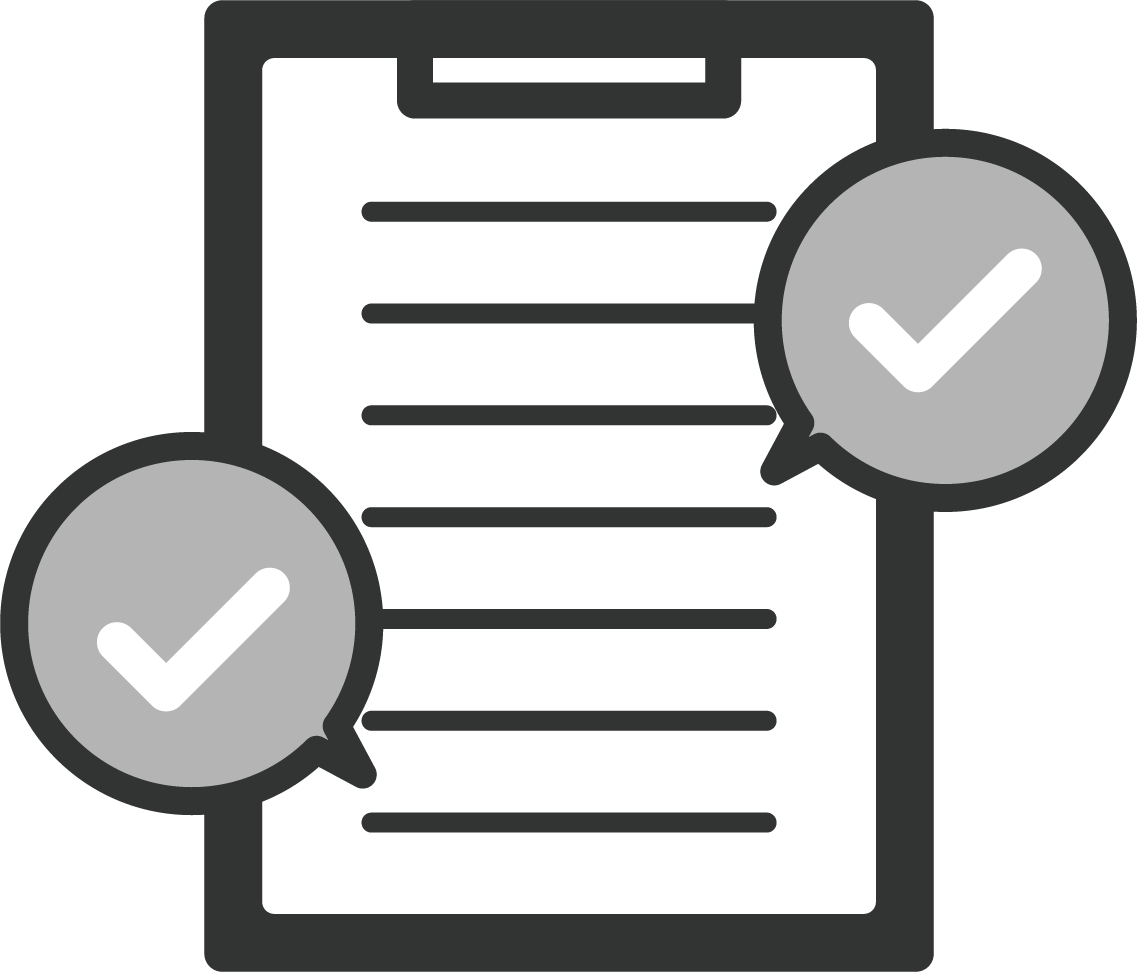

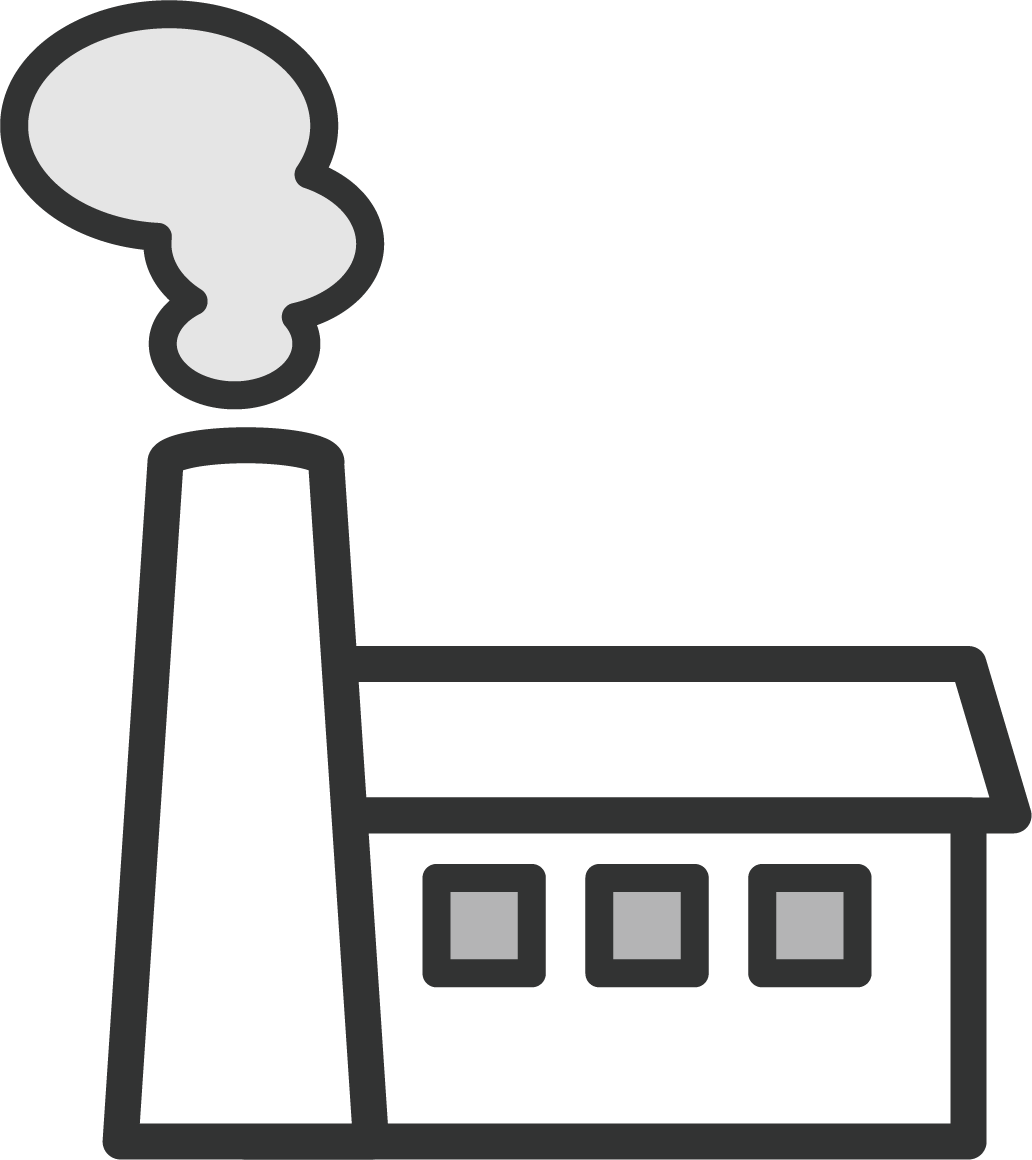
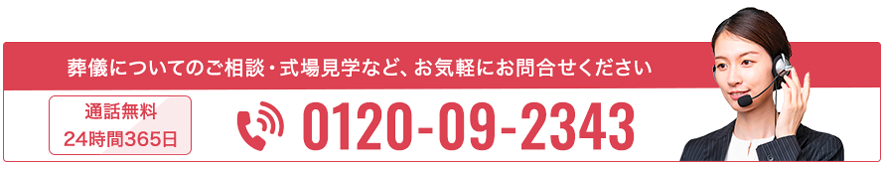
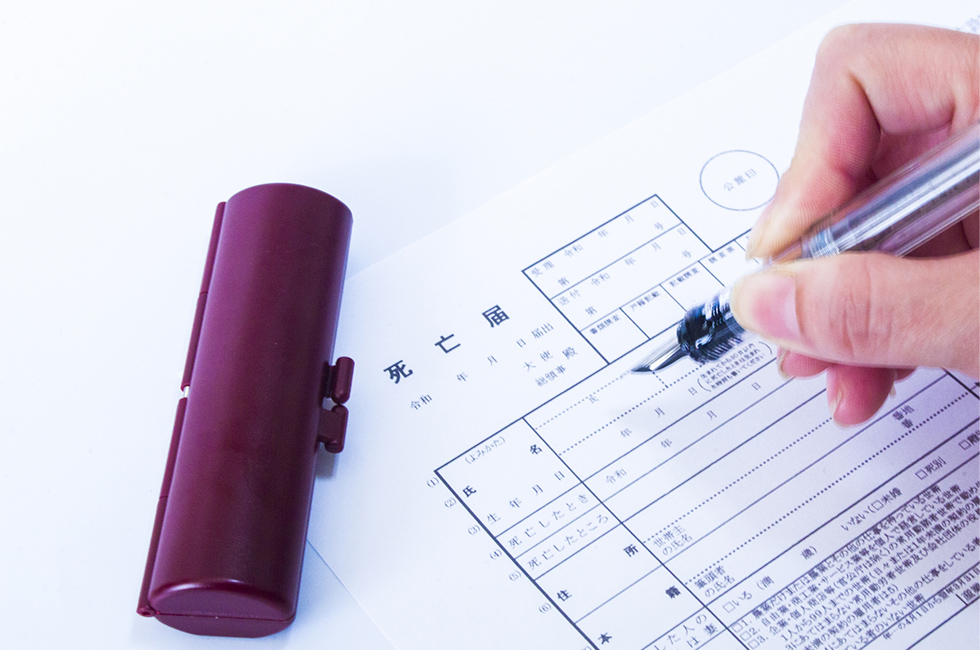












1月-600x450.jpg)
花-600x388.jpg)
冠婚葬祭-600x450.jpg)