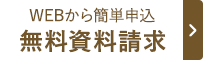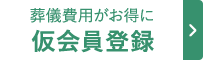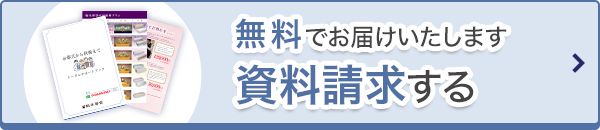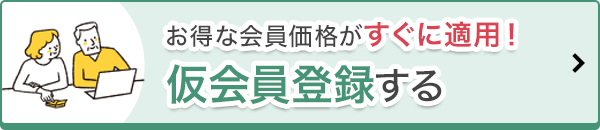盛岡の夏を彩る伝統行事「舟っこ流し」 | 盛岡市の葬儀・家族葬なら駒木葬祭
お葬式に関する豆知識 trivia
盛岡の夏を彩る伝統行事「舟っこ流し」
2025年08月31日
幻想的な夏の風物詩
盛岡の夏を代表する行事「舟っこ流し」は、毎年お盆の終わりに北上川で行われる供養の祭りです。
三百年以上の歴史を持つこの行事は、ご先祖の霊を送り、家族の健康や五穀豊穣を祈る「送り盆」の
象徴として受け継がれてきました。
起源と歴史
舟っこ流しの始まりは、盛岡藩主・南部行信の娘(麻久子姫/幕子姫)が川施餓鬼の大法事を行った
ことにあると伝えられています。
また1815年、北上川の氾濫で亡くなった遊郭の遊女を弔う舟流しが契機となり、以来、先祖供養だけでなく戦没者や災害の犠牲者の鎮魂の場としても営まれてきました。近年では東日本大震災の追悼も加わり、地域の祈りを受け継ぐ行事となっています。

行事の流れ
町内会や子供会が龍をかたどった舟を製作し、提灯やお札、遺影で飾り付けます。
当日、舟は明治橋の上流から川へ流され、炎を上げながら橋の下で燃え尽きます。水面に映る炎のゆらめきは幻想的で、命の尊さや生きていることへの感謝を静かに語りかけてくれます。

文化財としての価値
舟っこ流しはすでに盛岡市の指定無形民俗文化財であり、2014年には岩手県指定文化財の候補にも挙げられました。三百年余り続くこの行事は、盛岡の夏を象徴する伝統として、今も地域に深く根付いています。
命のつながりを見つめ直す機会
舟っこ流しは単なる夏祭りではなく、先祖を敬い、命の連なりを感じ、地域の絆を強める大切な場です。過去から未来へと続く祈りを次の世代へとつないでいくことが、心豊かな暮らしにつながるのではないでしょうか。

- 最近の投稿
- 全月別アーカイブ
-
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年6月
- 2022年3月
- 2021年11月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年4月
- 2021年3月